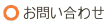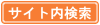| 1 |
1966 |
1 |
東条猛猪 |
自然保護 |
その他 |
|
47 |
| 2 |
1966 |
1 |
篭山京 |
自然保護運動考 |
その他 |
|
13 |
| 3 |
1966 |
1 |
井手賁夫 |
自然保護ということの意味と問題点 |
その他 |
|
16 |
| 4 |
1966 |
1 |
伊藤秀五郎 |
産業開発と自然保護 |
近代・産業 |
|
6 |
| 5 |
1966 |
1 |
犬飼哲夫 |
観光開発と裏大雪および知床の自然 |
近代・産業 |
|
9 |
| 6 |
1966 |
1 |
井手責夫 |
産業の発達と自然保護 |
近代・産業 |
|
5 |
| 7 |
1966 |
1 |
湊正雄 |
北の旅 |
その他 |
|
3 |
| 8 |
1966 |
1 |
秋山茂雄 |
自然保護と植物 |
植物 |
|
5 |
| 9 |
1966 |
1 |
犬飼哲夫 |
国土美化に関する米国大統領の教書の概要 |
その他 |
|
2 |
| 10 |
1966 |
1 |
|
写真 |
その他 |
|
2 |
| 11 |
1966 |
1 |
辻井達一 |
植物園-その現在と未来- |
植物 |
|
7 |
| 12 |
1966 |
1 |
石川俊夫 |
地質から見た自然保護 |
地質 |
|
13 |
| 13 |
1966 |
1 |
坂本直行 |
日高山脈の裏表 |
地質 |
|
14 |
| 14 |
1966 |
1 |
斎藤春雄 |
オオハクチョウ |
鳥類 |
|
6 |
| 15 |
1966 |
1 |
高橋延清 |
自然公園地域における森林風景の保全-支笏洞爺、阿寒を対象として- |
植物 |
|
9 |
| 16 |
1966 |
1 |
渡辺千尚 |
大雪山の高山昆虫 |
昆虫 |
|
23 |
| 17 |
1966 |
1 |
石川俊夫 |
網走国定公園 |
その他 |
|
5 |
| 18 |
1966 |
1 |
井手賁夫 |
阿寒国立公園 |
その他 |
|
2 |
| 19 |
1966 |
1 |
島倉亨次郎 |
道立厚岸自然公園と野付風蓮自然公園 |
その他 |
|
3 |
| 20 |
1967 |
2 |
東条猛猪 |
恵庭岳の滑降コースに思う |
その他 |
|
12 |
| 21 |
1967 |
2 |
犬飼哲夫 |
自然保護の国際的動向 |
その他 |
|
1 |
| 22 |
1967 |
2 |
渡辺千尚 |
自然保護上看過ごされがちな問題 |
その他 |
|
1 |
| 23 |
1967 |
2 |
明道博 |
生活と自然 |
その他 |
|
2 |
| 24 |
1967 |
2 |
林常夫 |
「北限大地」の前代話 |
その他 |
|
4 |
| 25 |
1967 |
2 |
安倍三史 |
風土のなかの人間 |
民族・アイヌ |
|
4 |
| 26 |
1967 |
2 |
東晃 |
アラスカの自然保護 |
その他 |
|
2 |
| 27 |
1967 |
2 |
山田幸男 |
海中の自然保護 |
その他 |
|
3 |
| 28 |
1967 |
2 |
村本輝夫、西浜雄二、華園康次、原秀雄、山口透 |
大雪山国立公園 |
その他 |
|
5 |
| 29 |
1967 |
2 |
今田敬一 |
私と自然 |
その他 |
|
7 |
| 30 |
1967 |
2 |
斎藤春雄 |
野生鳥獣保護のむずかしさ |
鳥類・哺乳類 |
|
4 |
| 31 |
1967 |
2 |
辻井達一 |
原生花園-群落の遷移に関する考察①- |
植物 |
|
8 |
| 32 |
1967 |
2 |
安部学 |
道東の鳥 |
鳥類 |
|
7 |
| 33 |
1967 |
2 |
山口透 |
北海道の山小屋 |
その他 |
|
7 |
| 34 |
1967 |
2 |
大谷吉雄 |
“茸”随想 |
菌 |
|
3 |
| 35 |
1967 |
2 |
重岡義雄 |
ヨーロッパの自然保護 |
その他 |
|
2 |
| 36 |
1967 |
2 |
田口鉄三 |
北海道における都市周辺の自然保護対策 |
その他 |
|
6 |
| 37 |
1967 |
2 |
犬飼哲夫、井手賁夫、渡辺千尚、田川隆、斎藤春雄、島倉亨次郎、籠山京、高橋延清、楡金幸三、辻井達一 |
昭和41年度調査報告書 |
その他 |
|
9 |
| 38 |
1967 |
2 |
井手賁夫 |
発足以来の北海道自然保護協会の歩みと反省 |
その他 |
|
4 |
| 39 |
1967 |
3 |
犬飼哲夫 |
自然保護の現在の問題点 |
その他 |
|
2 |
| 40 |
1967 |
3 |
山田真弓 |
自然保護雑感 |
その他 |
|
3 |
| 41 |
1967 |
3 |
望月達夫 |
回想の北の山 |
その他 |
|
4 |
| 42 |
1967 |
3 |
小川博三 |
自然保護と道路 |
その他 |
|
2 |
| 43 |
1967 |
3 |
高桑栄松 |
街路樹はなぜ枯れる? |
植物 |
|
4 |
| 44 |
1967 |
3 |
杉野目浩 |
英國の自然 |
その他 |
|
1 |
| 45 |
1967 |
3 |
犬飼哲夫 |
内陸水産資源の保護 |
その他 |
|
1 |
| 46 |
1967 |
3 |
俵浩三 |
自然保護と観光開発 |
近代・産業 |
|
5 |
| 47 |
1967 |
3 |
留岡清男 |
森林保護と教育 |
その他 |
|
1 |
| 48 |
1967 |
3 |
橋本昌利 |
保護の対策-北海道の自然公園- |
その他 |
|
2 |
| 49 |
1967 |
3 |
岡田正夫 |
ムカシトンボ絶滅記 |
昆虫 |
|
25 |
| 50 |
1967 |
3 |
村本輝夫、青木恵一、大場与志男、萩千賀子、山口透 |
湖沼と湿原・特集 |
その他 |
|
7 |
| 51 |
1967 |
3 |
松井善喜 |
北海道の道路並木① |
植物 |
|
5 |
| 52 |
1967 |
3 |
神原健 |
自然保護と気象 |
その他 |
|
1 |
| 53 |
1967 |
3 |
石城謙吉 |
北海道のイワナ類とその保護の問題 |
魚類 |
|
14 |
| 54 |
1967 |
3 |
一木万寿三 |
雪渓 |
その他 |
|
3 |
| 55 |
1967 |
3 |
谷口一芳 |
ニセコの展望 |
その他 |
|
1 |
| 56 |
1967 |
3 |
渡辺千尚 |
英國における昆虫類の保護 |
昆虫 |
|
6 |
| 57 |
1967 |
3 |
稲垣貫一 |
北海道の超塩基性岩地域の植物 |
植物 |
|
7 |
| 58 |
1967 |
3 |
辻井達一 |
渚にて-草原の遷移に関する考察②- |
植物 |
|
7 |
| 59 |
1967 |
3 |
井手賁夫 |
ルール炭鉱地帯の緑化について |
植物 |
|
2 |
| 60 |
1968 |
4 |
犬飼哲夫 |
自然保護と観光 |
近代・産業 |
|
4 |
| 61 |
1968 |
4 |
篭山京 |
北海道の自然保護と観光産業の関係 |
近代・産業 |
|
2 |
| 62 |
1968 |
4 |
大田正豁 |
国立公園の利用者と自然保護 |
その他 |
|
1 |
| 63 |
1968 |
4 |
小原豊明 |
膨張する温泉町 |
その他 |
|
2 |
| 64 |
1968 |
4 |
斎藤武 |
美しい空と水を |
その他 |
|
3 |
| 65 |
1968 |
4 |
山崎盛司 |
緑の花の街づくり-宇部市- |
植物 |
|
2 |
| 66 |
1968 |
4 |
植田英武 |
観光事業の現状と将来 |
近代・産業 |
|
5 |
| 67 |
1968 |
4 |
寺田喜助、遠藤昭太、辻井達一、山口透 |
木の花 |
植物 |
|
3 |
| 68 |
1968 |
4 |
松井善喜 |
北海道の道路並木② |
植物 |
|
4 |
| 69 |
1968 |
4 |
山田稔 |
自然と神秘性について |
その他 |
|
3 |
| 70 |
1968 |
4 |
中村幸雄 |
道有林の経営と自然保護 |
植物 |
|
3 |
| 71 |
1968 |
4 |
井手賁夫 |
ドイツ国立自然保護研究所 |
その他 |
|
1 |
| 72 |
1968 |
4 |
八木健三 |
火山と温泉の国・ニュージーランド |
地質 |
|
1 |
| 73 |
1968 |
4 |
丹保憲仁 |
一水屋の雑感 |
その他 |
|
2 |
| 74 |
1968 |
4 |
苫小牧郷土文化研究会 |
埋められたアオサギの営巣地 |
鳥類 |
|
4 |
| 75 |
1968 |
4 |
藤巻裕蔵 |
ウトナイ湖の水辺の鳥 |
鳥類 |
|
5 |
| 76 |
1968 |
4 |
辻井達一 |
川を野に、野を池に-草原の遷移に関する考察③- |
植物 |
|
6 |
| 77 |
1968 |
4 |
|
昭和42年度調査報告書 |
その他 |
|
3 |
| 78 |
1968 |
4 |
北大自然保護研究会 |
自然保護団体の果たすべき役割 |
その他 |
|
2 |
| 79 |
1969 |
5 |
井手賁夫 |
自然の静寂 |
その他 |
|
2 |
| 80 |
1969 |
5 |
斎藤雄一 |
西ドイツのフランクフルトの都市林 |
植物 |
|
2 |
| 81 |
1969 |
5 |
小関隆祺 |
ひとつの提案 |
その他 |
|
1 |
| 82 |
1969 |
5 |
渡辺安次 |
自然公園と自動車時代 |
近代・産業 |
|
2 |
| 83 |
1969 |
5 |
羽賀克己 |
国立公園指定と自然破壊 |
その他 |
|
5 |
| 84 |
1969 |
5 |
田川隆 |
竹に関する随想 |
植物 |
|
2 |
| 85 |
1969 |
5 |
阿部永 |
ネパール人と自然 |
その他 |
|
2 |
| 86 |
1969 |
5 |
辻井達一 |
アルペン・フロラ-草原の遷移に関する考察④- |
植物 |
|
3 |
| 87 |
1969 |
5 |
田中孝典、斎藤春雄、野村梧郎、村北利雄、森信也、村本輝夫 |
野鳥 |
鳥類 |
|
3 |
| 88 |
1969 |
5 |
斎藤春雄 |
野鳥と保護 |
鳥類 |
|
4 |
| 89 |
1969 |
5 |
林常夫 |
植物愛と人情のずれ |
植物 |
|
2 |
| 90 |
1969 |
5 |
江口完、光岡義彦、上田福雄、新田季利、瀬古海人、新妻博、原秀雄、長谷川雄七 |
会員通信 |
その他 |
|
2 |
| 91 |
1969 |
5 |
|
自然保護関係諸団体の沿革と規則抄 |
その他 |
|
1 |
| 92 |
1969 |
6 |
井手賁夫 |
自然保護運動のひとつの前進 |
その他 |
|
1 |
| 93 |
1969 |
6 |
小林三樹 |
自然保護か カラー・テレビか |
その他 |
|
3 |
| 94 |
1969 |
6 |
井上力太 |
大気汚染とその対策 |
その他 |
|
4 |
| 95 |
1969 |
6 |
斎藤禎男 |
札内川からの報告 |
その他 |
|
2 |
| 96 |
1969 |
6 |
鮫島惇一郎 |
自然保護とはなんだろう |
その他 |
|
4 |
| 97 |
1969 |
6 |
鈴木茂美 |
室蘭市の公害について |
近代・産業 |
|
1 |
| 98 |
1969 |
6 |
山口哲夫 |
もっと光を もっとみどりを |
植物 |
|
3 |
| 99 |
1969 |
6 |
田中瑞穂 |
洞爺湖 |
その他 |
|
3 |
| 100 |
1969 |
6 |
中島敏夫 |
キクイムシ |
昆虫 |
|
8 |
| 101 |
1969 |
6 |
田村剛 |
北海道の海中公園 |
その他 |
|
3 |
| 102 |
1969 |
6 |
辻寧昭 |
海藻資源の保護と育成 |
植物 |
|
12 |
| 103 |
1969 |
6 |
羽賀克巳 |
知床国立公園指定の意味 |
その他 |
|
3 |
| 104 |
1969 |
6 |
川床典輝 |
北海道の美しい山とイキイキした森林づくり |
植物 |
|
2 |
| 105 |
1969 |
6 |
野田四郎、吹上芳雄、上条一昭、住谷省三、高沢光雄、高橋誼、伊藤重右エ門 |
会員通信 |
その他 |
|
1 |
| 106 |
1969 |
6 |
坂本直行 |
ひとつの発見 |
その他 |
|
6 |
| 107 |
1969 |
6 |
大井道夫 |
東海自然歩道 |
その他 |
|
5 |
| 108 |
1969 |
6 |
武田久吉 |
札幌への初旅 |
その他 |
|
1 |
| 109 |
1969 |
6 |
金光正次 |
ヨセミテ渓谷で考えたこと |
その他 |
|
1 |
| 110 |
1969 |
6 |
辻井達一、伊藤浩司 |
自然保護へのチェック・シートメソードの採用 |
その他 |
|
1 |
| 111 |
1969 |
6 |
藤原英司 |
動物文学の史的展望 |
哺乳類 |
|
2 |
| 112 |
1969 |
6 |
|
ナショナル・トラストを設立し権限を与える法律 |
その他 |
|
1 |
| 113 |
1969 |
6 |
山口健児 |
北海道の地名 |
その他 |
|
3 |
| 114 |
1970 |
7 |
犬飼哲夫 |
自然界の相互関係 |
その他 |
|
1 |
| 115 |
1970 |
7 |
五十嵐彦仁 |
河川砂利採集のおよぼす影響と泥土の問題 |
地質 |
|
2 |
| 116 |
1970 |
7 |
吉田正人 |
産業公害と対策 |
近代・産業 |
|
1 |
| 117 |
1970 |
7 |
百武充 |
地球をこわさないために |
その他 |
|
1 |
| 118 |
1970 |
7 |
橋場文俊 |
人口問題について |
その他 |
|
1 |
| 119 |
1970 |
7 |
高桑栄松 |
公害と健康 |
近代・産業 |
|
1 |
| 120 |
1970 |
7 |
国松登 |
冬の樹木 |
植物 |
|
3 |
| 121 |
1970 |
7 |
谷口一芳 |
神威岬 |
その他 |
|
3 |
| 122 |
1970 |
7 |
千広俊幸、斎藤禎男、井後武、村本輝夫 |
会員通信 |
その他 |
|
1 |
| 123 |
1970 |
7 |
明道博、辻井達一 |
並木 |
植物 |
|
2 |
| 124 |
1970 |
7 |
大月源二 |
札樽バイパス高速道路の問題によせて |
その他 |
|
4 |
| 125 |
1970 |
7 |
中村幸雄 |
オリンピックまかり通る |
その他 |
|
2 |
| 126 |
1970 |
7 |
竹越俊文 |
ひらけることへのこだわり |
その他 |
|
1 |
| 127 |
1970 |
7 |
長谷川雄七 |
自然保護と保護すべき自然と |
その他 |
|
5 |
| 128 |
1970 |
7 |
一原有徳 |
山のベルドー氏 |
その他 |
|
1 |
| 129 |
1970 |
7 |
正富宏之 |
ニレとコマドリ |
鳥類 |
|
3 |
| 130 |
1970 |
7 |
三宅正紀 |
泥炭地と農業 |
近代・産業 |
|
2 |
| 131 |
1970 |
7 |
井手賁夫 |
協会の仕事と今後の課題 |
その他 |
|
2 |
| 132 |
1970 |
7 |
大場利夫 |
埋蔵文化財の保護 |
考古 |
|
2 |
| 133 |
1970 |
7 |
藤原英司 |
世界の自然を守る① |
その他 |
|
1 |
| 134 |
1970 |
7 |
ハインリッヒ・デーヴェス、訳・司馬威彦 |
自然保護と植物園 |
植物 |
|
4 |
| 135 |
1970 |
7 |
辻井達一 |
札幌の自然環境① |
その他 |
|
6 |
| 136 |
1970 |
7 |
上田福雄 |
自然とオリンピック |
その他 |
|
3 |
| 137 |
1970 |
7 |
|
ナショナル・トラスト法を修正する法律 |
その他 |
|
1 |
| 138 |
1970 |
7 |
|
ナショナル・トラストのうける特別免除 |
その他 |
|
0 |
| 139 |
1970 |
8 |
東条猛猪 |
北海道の広さ |
その他 |
|
3 |
| 140 |
1970 |
8 |
小林哲夫 |
河川の保護と魚 |
魚類 |
|
6 |
| 141 |
1970 |
8 |
木村敏男 |
感傷的保護論 |
その他 |
|
1 |
| 142 |
1970 |
8 |
渡辺千尚 |
自然保護・管理覚え書 |
その他 |
|
1 |
| 143 |
1970 |
8 |
雁田平吉 |
緑のまちづくり |
植物 |
|
5 |
| 144 |
1970 |
8 |
磯野則彦 |
札幌市における公園緑地 |
植物 |
|
2 |
| 145 |
1970 |
8 |
西村宗信 |
リュネブルグ自然保護地区見学記 |
その他 |
|
1 |
| 146 |
1970 |
8 |
小川均、中村幸雄、中須賀常雄、佐々木雅人、国松登、長谷川雄七 |
会員通信 |
その他 |
|
2 |
| 147 |
1970 |
8 |
俵浩三 |
川湯の自然教室 |
|
|
1 |
| 148 |
1970 |
8 |
井手賁夫 |
“自然保護”とは何か |
その他 |
|
2 |
| 149 |
1970 |
8 |
有沢浩 |
エゾライチョウ |
鳥類 |
|
7 |
| 150 |
1970 |
8 |
小川巌 |
ヒグマ研究集団発足す |
哺乳類 |
|
4 |
| 151 |
1970 |
8 |
藤原英司 |
世界の自然を守る② |
その他 |
|
1 |
| 152 |
1970 |
8 |
辻井達一 |
札幌の自然環境② |
その他 |
|
3 |
| 153 |
1970 |
8 |
浪田克之助 |
公園道路基準 |
その他 |
|
3 |
| 154 |
1971 |
9 |
犬飼哲夫 |
近年の観光開発と自然保護 |
近代・産業 |
|
2 |
| 155 |
1971 |
9 |
伊藤秀五郎 |
自然保護と教育 |
その他 |
|
1 |
| 156 |
1971 |
9 |
佐々木太一 |
学校教育における自然保護教育について |
その他 |
|
1 |
| 157 |
1971 |
9 |
村北利雄 |
教育実践“アオサギ生態観察日記”より |
鳥類 |
|
3 |
| 158 |
1971 |
9 |
山田文明 |
文化財と自然保護 |
その他 |
|
1 |
| 159 |
1971 |
9 |
千広俊幸 |
反省と提言 |
その他 |
|
1 |
| 160 |
1971 |
9 |
藤原英司 |
世界の自然を守る③ |
その他 |
|
3 |
| 161 |
1971 |
9 |
辻寧昭、笹本洋三、藤原英司、斎藤禎男、安田美穂子、中田幹男 |
会員通信 |
その他 |
|
9 |
| 162 |
1971 |
9 |
楡金幸三、大場与志男、石川俊夫、山口透、根本忠寛、北海道教育委員会 |
柱状節理 |
地質 |
|
4 |
| 163 |
1971 |
9 |
湊正雄 |
モンタナで考えたこと |
その他 |
|
2 |
| 164 |
1971 |
9 |
橋本誠二 |
山岳の保護と登山 |
その他 |
|
4 |
| 165 |
1971 |
9 |
大場利夫 |
札樽地域における埋蔵文化財の保護について |
考古 |
|
1 |
| 166 |
1971 |
9 |
|
自然保護計画策定調査報告書 |
その他 |
|
1 |
| 167 |
1972 |
10 |
伊藤秀五郎 |
21世紀の選択 |
その他 |
|
1 |
| 168 |
1972 |
10 |
芳賀良一 |
北海道東部・十勝の自然 |
その他 |
|
20 |
| 169 |
1972 |
10 |
宗像英雄 |
道南の自然と保護問題 |
その他 |
|
4 |
| 170 |
1972 |
10 |
田中瑞穂 |
釧路に住む |
その他 |
|
6 |
| 171 |
1972 |
10 |
門脇松次郎 |
美々川流域調査報告 |
その他 |
|
8 |
| 172 |
1972 |
10 |
斎藤春雄 |
湿原に想う |
その他 |
|
1 |
| 173 |
1972 |
10 |
三浦正幸 |
北海道春ニシンの消滅と森林 |
魚類・植物 |
|
5 |
| 174 |
1972 |
10 |
古後順子、斎藤真理子、吉田勝、田尻聡子、高畑滋、西村格、小川巖 |
会員通信 |
その他 |
|
2 |
| 175 |
1972 |
10 |
鮫島惇一郎 |
山の花 |
植物 |
|
6 |
| 176 |
1972 |
10 |
石川俊夫 |
北チリの旅 |
その他 |
|
1 |
| 177 |
1972 |
10 |
明峯哲夫 |
自然保護から自然奪還へ |
その他 |
|
3 |
| 178 |
1972 |
10 |
小川均 |
自然保護と地域住民 |
その他 |
|
1 |
| 179 |
1972 |
10 |
斎藤雄一 |
森林の種類 |
植物 |
|
5 |
| 180 |
1972 |
10 |
藤原英司 |
世界の自然を守る④ |
その他 |
|
1 |
| 181 |
1972 |
10 |
石川洽、山中京子、横井匡彦、白鳥勝美、後藤元伸 |
自然保護はこれでいいのか |
その他 |
|
3 |
| 182 |
1972 |
10 |
芳賀良一 |
裏大雪・然別湖周辺の自然保護 |
その他 |
|
6 |
| 183 |
1972 |
10 |
石野道男 |
人間の知恵とはなにか |
その他 |
|
2 |
| 184 |
1972 |
10 |
|
北海道自然保護セミナーの報告 |
その他 |
|
1 |
| 185 |
1973 |
11 |
井手賁夫 |
これからの自然保護 |
その他 |
|
2 |
| 186 |
1973 |
11 |
斎藤義信 |
自然保護運動と教会 |
その他 |
|
1 |
| 187 |
1973 |
11 |
金田平 |
採集より観察を |
その他 |
|
2 |
| 188 |
1973 |
11 |
宮崎是 |
高速道路と景観構成 |
近代・産業 |
|
1 |
| 189 |
1973 |
11 |
太田重良 |
治山の工法と景観保全 |
近代・産業 |
|
2 |
| 190 |
1973 |
11 |
森樊須 |
ダニと植物 |
無脊椎動物・植物 |
|
3 |
| 191 |
1973 |
11 |
藤巻裕蔵、松岡茂 |
ウトナイト沼の冬と水鳥類 |
鳥類 |
|
3 |
| 192 |
1973 |
11 |
岩崎四郎、金子明石、大原葉子、龍造寺直子、小池保子、中村芳男、太田正豁 |
会員通信 |
その他 |
|
3 |
| 193 |
1973 |
11 |
村本輝夫、熊谷剛、稗田義貞、萩千賀、鮫島惇一郎、山口透 |
北海道の山小屋 |
その他 |
|
6 |
| 194 |
1973 |
11 |
山口透 |
山と山小屋 |
その他 |
|
2 |
| 195 |
1973 |
11 |
辻井達一 |
二つの池 |
その他 |
|
2 |
| 196 |
1973 |
11 |
|
アラスカ探検学校 |
その他 |
|
2 |
| 197 |
1973 |
11 |
正冨宏之 |
アーチボルド氏の報告について |
その他 |
|
1 |
| 198 |
1973 |
11 |
|
タンチョウ保護に関する報告 |
鳥類 |
|
4 |
| 199 |
1973 |
11 |
藤原英司 |
世界の自然を守る⑤ |
その他 |
|
1 |
| 200 |
1974 |
12 |
村本輝夫 |
旭岳・北部大雪山の南望 |
その他 |
|
4 |
| 201 |
1974 |
12 |
伊藤秀五郎 |
自然保護の要諦 |
その他 |
|
1 |
| 202 |
1974 |
12 |
国府谷盛明 |
大雪山の地質 |
地質 |
|
5 |
| 203 |
1974 |
12 |
桜井兼市 |
大雪山の気象 |
その他 |
|
4 |
| 204 |
1974 |
12 |
鮫島惇一郎 |
大雪山の植物 |
植物 |
|
9 |
| 205 |
1974 |
12 |
小川巌 |
大雪山の動物 |
昆虫・鳥類哺乳類 |
|
8 |
| 206 |
1974 |
12 |
長谷川雄七 |
大雪山国立公園の沿革 |
その他 |
|
4 |
| 207 |
1974 |
12 |
伊藤秀五郎 |
大雪山登山史 |
その他 |
|
4 |
| 208 |
1974 |
12 |
西村格 |
大雪山縦貫道路建設反対運動の経過と今後の問題点 |
その他 |
|
4 |
| 209 |
1974 |
12 |
井手賁夫 |
大雪山縦貫道路と北海道自然保護協会 |
その他 |
|
2 |
| 210 |
1974 |
12 |
渡辺伊沙子、橋場文俊、松村雄、相場幸子、伊藤伊津子、國松登、荒沢勝太郎、山田明人、早川さかゑ |
会員通信 |
その他 |
|
16 |
| 211 |
1974 |
12 |
新妻昭夫 |
忘れられた動物-ゼニガタアザラシの実態- |
哺乳類 |
|
2 |
| 212 |
1974 |
12 |
石崎貞子 |
日高ヒマラヤ・カナディアン・ロッキー |
その他 |
|
1 |
| 213 |
1974 |
12 |
八木健三 |
アメリカの国立公園 |
その他 |
|
1 |
| 214 |
1974 |
12 |
村野紀雄 |
野幌森林公園と自然保護 |
その他 |
|
3 |
| 215 |
1974 |
12 |
小川均 |
西表島の自然保護 |
その他 |
|
1 |
| 216 |
1974 |
12 |
野田豊子 |
野鳥の日記から |
鳥類 |
|
3 |
| 217 |
1974 |
12 |
向井成司 |
日高の牧場に立ちて |
その他 |
|
1 |
| 218 |
1974 |
12 |
藤原英司 |
世界の自然を守る⑥ |
その他 |
|
1 |
| 219 |
1975 |
13 |
伊藤秀五郎 |
北海道の森林保全 |
植物 |
|
3 |
| 220 |
1975 |
13 |
桜井兼市 |
大雪山における気象の研究 |
その他 |
|
3 |
| 221 |
1975 |
13 |
石川俊夫 |
大雪山地学研究史 |
地質 |
|
5 |
| 222 |
1975 |
13 |
藤木忠美 |
大雪山構造土地形研究小史 |
地質 |
|
5 |
| 223 |
1975 |
13 |
佐藤謙 |
大雪山の植物研究史 |
植物 |
|
5 |
| 224 |
1975 |
13 |
阿部永 |
大雪山の動物研究史 |
哺乳類・鳥類。両棲類(両生類)・爬虫類・その他 |
|
11 |
| 225 |
1975 |
13 |
渡辺千尚 |
大雪山の昆虫研究覚え書 |
昆虫 |
|
14 |
| 226 |
1975 |
13 |
西村格、谷井保子、菊地隆司、大木敏嗣、藤巻裕蔵、山本正、駒井勉 |
会員通信 |
その他 |
|
2 |
| 227 |
1975 |
13 |
三浦二郎 |
根室自然保護教育研究会のこれまでとこれから |
その他 |
|
3 |
| 228 |
1975 |
13 |
坂本直行 |
失われてゆく生活の中の自然 |
その他 |
|
8 |
| 229 |
1975 |
13 |
斎藤雄一 |
北海道の森林生産と自然保護 |
植物 |
|
3 |
| 230 |
1975 |
13 |
俵浩三 |
氷河湾の印象 |
その他 |
|
1 |
| 231 |
1975 |
13 |
井手賁夫 |
自然保護と今後の政治 |
その他 |
|
1 |
| 232 |
1975 |
13 |
森田弘彦 |
羊ヶ丘の植物相 |
植物 |
|
6 |
| 233 |
1975 |
13 |
村本輝夫 |
自然開発、破壊保護雑感 |
その他 |
|
1 |
| 234 |
1975 |
13 |
高畑滋 |
木地挽山のシバ牧野保護について |
植物 |
|
3 |
| 235 |
1975 |
13 |
北川芳男 |
ファヒネ島の自然 |
その他 |
|
1 |
| 236 |
1975 |
13 |
秋田稔 |
札幌新道と教育環境 |
その他 |
|
1 |
| 237 |
1975 |
13 |
青地晨 |
観光開発と自然破壊 |
近代・産業 |
|
1 |
| 238 |
1975 |
13 |
陶三男 |
然別湖の自然を |
その他 |
|
2 |
| 239 |
1975 |
13 |
藤村俊彦 |
東ヌプカウシ山の自然保護 |
その他 |
|
5 |
| 240 |
1975 |
13 |
小川均 |
自然にかえる子供たち |
その他 |
|
1 |
| 241 |
1975 |
13 |
四十万谷吉郎 |
羊ヶ丘の鳥 |
植物 |
|
2 |
| 242 |
1975 |
13 |
青柳正英 |
サロベツ原野と開発 |
その他 |
|
1 |
| 243 |
1975 |
13 |
小川巌 |
全国自然保護連合大会(第4回)に参加して |
その他 |
|
1 |
| 244 |
1975 |
14 |
石川俊夫 |
自然公園と車道 |
近代・産業 |
|
1 |
| 245 |
1975 |
14 |
桑原義晴 |
自然保護教育と採集のあり方 |
その他 |
|
2 |
| 246 |
1975 |
14 |
野田四郎 |
採集と観察 |
その他 |
|
2 |
| 247 |
1975 |
14 |
三浦二郎 |
学校における自然保護教育と採集 |
その他 |
|
1 |
| 248 |
1975 |
14 |
伊藤秀五郎 |
〈詩〉草木叙情 |
その他 |
|
1 |
| 249 |
1975 |
14 |
国松登、俵浩三、野田四郎、山根正気、小川巌 |
《座談会》採集をめぐる諸問題 |
その他 |
|
3 |
| 250 |
1975 |
14 |
|
“自然保護教育と採集のあり方”に関するアンケート |
その他 |
|
1 |
| 251 |
1975 |
14 |
梅田安治 |
アラスカ-点と線- |
その他 |
|
1 |
| 252 |
1975 |
14 |
斎藤禎男、百武充、原田輝治、橋場文俊、竹内恒夫、村本輝夫、森田弘彦、城殿博 |
会員通信 |
その他 |
|
2 |
| 253 |
1975 |
14 |
クマゲラ観察グループ |
野幌森林公園のクマゲラ一家 |
鳥類 |
|
2 |
| 254 |
1975 |
14 |
正富宏之 |
アメリカの保護区見物記 |
その他 |
|
1 |
| 255 |
1975 |
14 |
伊藤秀五郎 |
北海道の開発と自然保護についての感想 |
近代・産業 |
|
2 |
| 256 |
1975 |
14 |
鮫島惇一郎 |
遺伝子給源の保護 |
その他 |
|
1 |
| 257 |
1975 |
14 |
高沢光雄 |
山で考えたこと |
その他 |
|
1 |
| 258 |
1975 |
14 |
五味茂 |
自然保護活動優秀団体の表彰にあたって |
その他 |
|
1 |
| 259 |
1975 |
14 |
八木健三 |
オーストラリアの自然と自然保護 |
その他 |
|
1 |
| 260 |
1976 |
15 |
村本輝夫 |
釧路湿原・サロベツ原野 |
その他 |
|
4 |
| 261 |
1976 |
15 |
石川俊夫 |
湿原の魅力 |
その他 |
|
4 |
| 262 |
1976 |
15 |
岡崎由夫 |
釧路湿原とその地形・地質 |
地質 |
|
2 |
| 263 |
1976 |
15 |
田中瑞穂 |
釧路湿原の植生と植物景観 |
植物 |
|
7 |
| 264 |
1976 |
15 |
橋本正雄 |
湿原に生きる動物たち |
昆虫・鳥類・両棲類(両生類) |
|
19 |
| 265 |
1976 |
15 |
山代昭三 |
釧路湿原の魚類 |
魚類 |
|
12 |
| 266 |
1976 |
15 |
荒沢勝太郎 |
釧路湿原の花 |
植物 |
|
3 |
| 267 |
1976 |
15 |
田中瑞穂 |
霧多布湿原・落石湿原・ユルリ島湿原 |
その他 |
|
5 |
| 268 |
1976 |
15 |
辻井達一 |
サロベツ原野 |
その他 |
|
4 |
| 269 |
1976 |
15 |
大場利夫 |
サロベツ遺跡 |
考古 |
|
5 |
| 270 |
1976 |
15 |
辻井達一 |
風蓮湿原 |
その他 |
|
3 |
| 271 |
1976 |
15 |
田中瑞穂 |
三本木湿原(標津町) |
その他 |
|
4 |
| 272 |
1976 |
15 |
三浦二郎 |
標津川湿原 |
その他 |
|
1 |
| 273 |
1976 |
15 |
桜田純司 |
標津俵橋泥炭地 |
地質 |
|
1 |
| 274 |
1976 |
15 |
羽田恭子、渡部誠一郎、土屋秀人、小山政弘、青井俊樹 |
会員通信 |
その他 |
|
1 |
| 275 |
1976 |
15 |
鮫島惇一郎 |
沼の原と沼の平の湿原 |
その他 |
|
4 |
| 276 |
1976 |
15 |
成田新太郎 |
浮島湿原の調査(第1年次)をおえて |
その他 |
|
3 |
| 277 |
1976 |
15 |
斎藤実 |
原始ヶ原湿原 |
その他 |
|
3 |
| 278 |
1976 |
15 |
国兼治徳 |
雨竜沼湿原 |
その他 |
|
6 |
| 279 |
1976 |
15 |
辻井達一 |
石狩低地帯の湿原 |
その他 |
|
2 |
| 280 |
1976 |
15 |
桑原義晴 |
神仙沼・大谷地湿原の植生 |
植物 |
|
4 |
| 281 |
1976 |
15 |
宗像英雄 |
横津岳の湿原 |
その他 |
|
3 |
| 282 |
1976 |
15 |
松田彊 |
天塩国中峰の平湿原 |
その他 |
|
5 |
| 283 |
1976 |
15 |
辻井達一 |
道北の湿原 |
その他 |
|
4 |
| 284 |
1976 |
15 |
梅田安治 |
湿原はどう変わっていくか |
その他 |
|
2 |
| 285 |
1976 |
15 |
高畑滋 |
自然を破壊するバイパス計画に反対する |
その他 |
|
1 |
| 286 |
1976 |
15 |
伊藤誠夫 |
道内スキー場の利用状況と自然環境 |
近代・産業 |
|
2 |
| 287 |
1976 |
15 |
犬飼哲夫 |
中央アジアのシルクロード紀行 |
その他 |
|
1 |
| 288 |
1977 |
16 |
八木健三 |
緑と学園 |
その他 |
|
1 |
| 289 |
1977 |
16 |
干場豊繁 |
釧路湿原のおかれている現状 |
その他 |
|
3 |
| 290 |
1977 |
16 |
高畑滋 |
農地開発と環境保全 |
近代・産業 |
|
1 |
| 291 |
1977 |
16 |
梅田安治 |
咲かなかったサロベツの花 |
植物 |
|
4 |
| 292 |
1977 |
16 |
宗像英雄 |
函館付近における自然保護運動経緯の概要 |
その他 |
|
1 |
| 293 |
1977 |
16 |
伊藤秀五郎 |
夏三題(詩) |
その他 |
|
1 |
| 294 |
1977 |
16 |
森田弘彦、松本一和、加納菜穂子、原田輝治、岩垂悟、小野寺敬子、三木昇、辻井達一 |
会員通信 |
その他 |
|
2 |
| 295 |
1977 |
16 |
村野紀雄 |
“野幌森林公園のクマゲラ一家”その後 |
鳥類 |
|
5 |
| 296 |
1977 |
16 |
八木健三 |
「北の山・続篇」を読んで |
その他 |
|
2 |
| 297 |
1977 |
16 |
俵浩三 |
北海道自然保護小史(一) |
その他 |
|
5 |
| 298 |
1977 |
16 |
滝口亘 |
札幌オリンピックのいやされぬ爪痕 |
その他 |
|
9 |
| 299 |
1977 |
16 |
|
やまぼうしの会 |
その他 |
|
1 |
| 300 |
1977 |
16 |
加納登 |
ストックホルムはお好きですか? |
その他 |
|
1 |
| 301 |
1977 |
16 |
井手賁夫 |
北海道自然保護協会の設立とその前後の自然保護の動き |
その他 |
|
2 |
| 302 |
1978 |
17 |
石川俊夫 |
山・スキー・自然 |
その他 |
|
1 |
| 303 |
1978 |
17 |
加藤勇太郎 |
北海道の農業を考える〔前〕 |
近代・産業 |
|
1 |
| 304 |
1978 |
17 |
河村章人 |
私の「いわゆる鯨・捕鯨問題」 |
近代・産業 |
|
1 |
| 305 |
1978 |
17 |
三股正年 |
道産和種馬(どさんこ)余聞 |
哺乳類 |
|
4 |
| 306 |
1978 |
17 |
八戸芳夫 |
ドサンコの生い立ち |
哺乳類 |
|
3 |
| 307 |
1978 |
17 |
市川正良 |
森林と開発 |
近代・産業 |
|
2 |
| 308 |
1978 |
17 |
上田五郎 |
田中瑞穂先生を悼む |
その他 |
|
3 |
| 309 |
1978 |
17 |
橋場文俊、村野紀雄、石島忍、高沢光雄、遠藤太郎、百武充、家登美智子、大西英一、村本輝夫 |
会員通信 |
その他 |
|
1 |
| 310 |
1978 |
17 |
綱島俊 |
大雪山をめぐる水力発電 |
近代・産業 |
|
3 |
| 311 |
1978 |
17 |
土屋文男 |
庭の小鳥 |
鳥類 |
|
2 |
| 312 |
1978 |
17 |
俵浩三 |
北海道自然保護小史(二) |
その他 |
|
7 |
| 313 |
1978 |
17 |
城殿博 |
南米最南端の地、フエゴ島の人と自然 |
その他 |
|
2 |
| 314 |
1979 |
18 |
八木健三 |
発展途上国と自然保護 |
その他 |
|
1 |
| 315 |
1979 |
18 |
加藤勇太郎 |
北海道の農業を考える〔後〕 |
近代・産業 |
|
1 |
| 316 |
1979 |
18 |
三木昇 |
ネパールの林 |
その他 |
|
1 |
| 317 |
1979 |
18 |
長井博 |
雲南動物研究所と植物研究所を尋ねて |
植物 |
|
2 |
| 318 |
1979 |
18 |
遠藤太郎、久保田敏夫、石井次郎 |
会員通信 |
その他 |
|
1 |
| 319 |
1979 |
18 |
村野紀雄、藤林忠雄 |
野幌森林公園のクマゲラ一家(その3) |
鳥類 |
|
4 |
| 320 |
1979 |
18 |
俵浩三 |
北海道自然保護小史(三) |
その他 |
|
5 |
| 321 |
1979 |
18 |
札掛太郎 |
全国自然保護連合のこと |
その他 |
|
1 |
| 322 |
1979 |
18 |
川合季彦 |
エルザ自然保護の会の誕生と活動 |
その他 |
|
4 |
| 323 |
1979 |
18 |
市川正良 |
自然は誰のものか-滝野国営公園を考える- |
その他 |
|
1 |
| 324 |
1979 |
18 |
八木健三 |
78年日米民間環境会議 |
その他 |
|
1 |
| 325 |
1979 |
18 |
札木照一朗 |
自然保護分科会に参加して |
その他 |
|
1 |
| 326 |
1980 |
19 |
石川俊夫 |
オホーツクの自然 |
その他 |
|
2 |
| 327 |
1980 |
19 |
吉崎昌一 |
川と人間 |
その他 |
|
1 |
| 328 |
1980 |
19 |
河村章人 |
少数鯨族-カワイルカ |
哺乳類 |
|
4 |
| 329 |
1980 |
19 |
一原有徳 |
登山と河川-自然保護への疑問- |
その他 |
|
0 |
| 330 |
1980 |
19 |
本田明二 |
渓流釣りから見た北海道の川 |
その他 |
|
3 |
| 331 |
1980 |
19 |
小宮山英重 |
川の構造と魚の生活 |
魚類 |
|
6 |
| 332 |
1980 |
19 |
高橋剛一郎 |
淡水魚の保護と流域保全 |
魚類 |
|
10 |
| 333 |
1980 |
19 |
小川芳昭 |
社会のなかの河川 |
その他 |
|
3 |
| 334 |
1980 |
19 |
島田明英 |
石狩川の鳥 |
鳥類 |
|
5 |
| 335 |
1980 |
19 |
堀淳一 |
地図に見る北海道の川 |
その他 |
|
3 |
| 336 |
1980 |
19 |
大山明、中野徹三、橋場文俊、八木健三、札木照一朗、原田輝治 |
会員通信 |
その他 |
|
3 |
| 337 |
1980 |
19 |
泉重雄 |
自然保護講座(第1学期)を終えて |
その他 |
|
1 |
| 338 |
1980 |
19 |
高橋英紀 |
フロリダ半島エバーグレイズの農業開発と自然保護 |
近代・産業 |
|
1 |
| 339 |
1980 |
19 |
紺谷友昭 |
採石と山林保護の諸問題 |
近代・産業 |
|
1 |
| 340 |
1981 |
20 |
門脇松次郎 |
道路 |
近代・産業 |
|
2 |
| 341 |
1981 |
20 |
伊藤蔵吉 |
北海道における道路行政と自然保護 |
近代・産業 |
|
2 |
| 342 |
1981 |
20 |
大澤肇 |
今後の自然環境の保全と道路建設 |
近代・産業 |
|
1 |
| 343 |
1981 |
20 |
海谷俊彦 |
林業振興と林道 |
近代・産業 |
|
1 |
| 344 |
1981 |
20 |
木田和幸 |
北海道における高速道路と道路造園 |
近代・産業 |
|
2 |
| 345 |
1981 |
20 |
俵浩三 |
自然歩道 |
その他 |
|
2 |
| 346 |
1981 |
20 |
梅田安治 |
みち・さまざま |
その他 |
|
2 |
| 347 |
1981 |
20 |
|
〈質問の窓〉 |
その他 |
|
1 |
| 348 |
1981 |
20 |
森山軍治郎 |
北海道の道路私史 |
その他 |
|
6 |
| 349 |
1981 |
20 |
一原有徳 |
山の道、五題 |
その他 |
|
2 |
| 350 |
1981 |
20 |
吉田勇治 |
日高への道 |
その他 |
|
4 |
| 351 |
1981 |
20 |
八木健三 |
なぜ「日高横断道路反対」なのか |
その他 |
|
4 |
| 352 |
1981 |
20 |
阿部永、矢口以文、札木照一朗 |
会員通信 |
その他 |
|
1 |
| 353 |
1981 |
20 |
小高達雄 |
「自然」のこと「文化」のこと |
その他 |
|
1 |
| 354 |
1981 |
20 |
|
〈座談会〉会誌第20号を迎えて |
その他 |
|
1 |
| 355 |
1981 |
20 |
大山明 |
「狸台林道」を視る |
その他 |
|
13 |
| 356 |
1981 |
20 |
紺谷友昭 |
分裂する私有林-札幌市内の例 |
植物 |
|
17 |